|
2011.3.11の東北・関東大震災に伴い、東電福島第1発電所で津波による外部電源喪失に端を発した事故が生じております。さすがに10日以上経ち、いろいろな解説(怪説)を見かけるようになりました。自分で全てを語れるほど学識はないのですが、お友達から「あれ、ホントですか」と聞かれたことに応えていったメイルが結構溜まりましたので、前後不順で書き留めてみます。 初版 2011/03/27 追補 2011/03/29 東電誤発表 追補 2011/03/30 Sr-90の懸念を追加 |
東電誤発表:1000万倍? Co-56? I-134? Cs-134?(報道多数)汚染された漏洩水の中の放射性核種の分析に関して、東電の発表→安全委員会から「な事はないだろ、もっぺん測ってみ」→「すいません間違いでした」が何回かあったようです。この手の分析、γ線のスペクトロメトリーでやる訳ですが、限られた情報から東電の具体的な間違いのプロセスを推定してみました。(かなりあてずっぽうがはいっています) 得られたピークは、本当はこれだった。 ●56Co (半減期 77.27 d) γ線エネルギー 846.771keV 放出確率 100% それを、別な核種と考えて解析すると; 【古い説明】 ●134I (半減期 52.5 m) γ線エネルギー 847.025keV 放出確率 95.4% →半減期補正で、試料採取時の線量を逆算すると、異常に高Bq数に。 (例えば、24時間前とすると測定時の180,000,000倍) 【新しい説明】 ●134Cs (半減期 2.0648 y) γ線エネルギー 847.025keV 放出確率 0.00030% →こんな、放出確率の少ないγ線がいっぱい出ているので、もとの放射能(Bq数)はきっとすごい、と思ってしまった。 いずれにせよ、「測定し直した」までは必要なく、既に取得済みのスペクトルの再解析で充分なはず。というわけで、厳密には「測定ミス」→「解析ミス」 個人的には、古い説明の方なら、少し同情します(まじめに半減期補正している所など、むしろ良心的)。しかし、これだけ半減期の短い核種が大量に、というのを安易に結論付けるのは、少々あさはか。 一方、新しい説明の通りなら、大馬鹿者。 本来、134Csは、こんな放出確率の低いγ線で測るべきではなく、近所にもっと手頃なピークがあります。そっちを見れば、134Csがホントかどうかは、スグわかったはずで、当然やるべきでした。 (もっとも、試料は雑多なFPの塊なので、いろんなピークが林立していてなかなか、同定は難しかったのかも知れませんが・・・。) ▲もっとメジャーな134Csのγ線: γ線エネルギー 604.721keV 放出確率 97.62% γ線エネルギー 795.864keV 放出確率 85.53% γ線のエネルギーと放出確率は下記で取得。 http://nucleardata.nuclear.lu.se/nucleardata/toi/index.asp −−−−−−−− ・・・と新しい説明の解釈も違う? そもそも「ホントはCs-134でした」って? もう、わけわかめ。これだけ混乱した発表するくらいなら、生データ:γ線のスペクトルデータも出して欲しい。 そもそも、γ線スペクトロメトリーは、コンデンサー(ダイオードに逆電圧掛けるみたいな)の絶縁をγ線が破壊して電流が流れる、と、その電流の量からγ線のエネルギーを逆算する、ってなことをやって測ってます。おおざっぱな仕掛けは、ガイガーカウンター(電流量を測ることまではしませんが)や変ったところではイオンゲージ(真空ゲージ→励起場一定で残留ガス圧を測る)も、まぁ、似たようなもの。(似たようなもの!:本ウェブサイトの基本コンセプト) で、このような測定を毎秒何百回も機械が自動で繰り返して、γ線のエネルギー分布のデータを蓄積していきます。最近の装置はその後の解析も大変親切に出来ているらしく、「このピークはコバルト60です」、みたいなことを教えてくれて、定量もかなり自動でやってくれるとのことなのですが、やはり機械のやること、上記のようなエネルギーの接近したような話の時には、様々な状況からピークの同定を総合的判断でやらねば成りません。と、ここから先はありがちな年寄りのぼやきなのですが、もれ承るところによりますと、今、こういうデータを出している奴らはマニュアル通り機械の自動解析ばっかりで、いわゆる総合的判断が全く出来ない、という話もなんとなく。 まぁ、「充分寝てない」、という状況も容易に想像できますので、あまり悪くは言いません。それに、良く検討していると、その間を「データ隠し」と言われるし、スグ出して間違っていると、こうやっていじめられるし、それはそれで充分気の毒。 それにしても、発表されている核種は、運転終了後2週間程度の燃料から漏れてくるものとして、適当なものなのかな? 例えば、そろそろTe-132、Y-91、Pr-143などもメジャーな構成成分になってくる(参考文献)はずなのですが、ちゃんとその辺、気にして測ってる? ・・・と、そういえば Sr-90 はちゃんと測っているのかな? 内部被曝上、重要な核種ですが(化学的性質がカルシウムに似ているので骨に沈着)、β線しか出さぬ核種なのでγ線スペクトロメトリーだけでは追いかけきれず、多少の化学操作を伴ったβ線による検出・定量が必要な核種のハズですが。 あのγ線のスペクトルさえまともに扱えない連中がここまで気が廻っているだろうか? 誤報:Zr-95検出、被覆管破損!(読売)曰く東京電力は24日、福島第一原発の放水口近くで採取した海水から、放射性ジルコニウム95を微量検出したと発表した。 ジルコニウムは核燃料の被覆管に使われており、冷却水が失われて高温になった使用済み核燃料の被覆管の一部が溶けて、大量放水された海水に混じって海に流れ込んだ可能性がある。 Zr-95は代表的な核分裂生成物(ウラン由来)です。 被覆管ジルカロイ由来ではないハズ。 近大のせんせは、被覆管が損傷している(中身がもれちゃった?)と までは言っていますが、検出したZr95がその被覆管由来とは言っていない。 本件も記者のハヤトチリと思われます。 所詮、メディア側のポテンシャルは、この程度? 当局側がこの程度のエラーをしたときは、鬼の首のくせに。 U235核分裂後の、放射能成分の推移はこちら; Zr-95は、数日後以降は、ベクレル数では 5番目くらいに多いFP核種です。 FP:核分裂生成物 (Fission Product) 原子力学会の資料(使用済みMOXの安全性を議論しているもの) 原子炉停止後、4日時点でのγ線源強度を決める支配的なFPは95Zr、95Nb、140Laです。 UCSB Ben Monreal教授の解説一部では「良い解説である」と評判のもので、有志の方による和訳版も作られています。しかし、少なくとも小生には若干の問題が感じられ、そもそもこの「解説の解説」を書こうと思ったきっかけの作品であります。問題点は、主に2つのレベルに分けられ、 1.科学的に明白な誤り。但し、多くはそんなに根の深い話ではない。 2.科学的な誤りと言うよりも、総論解説としての妥当性の問題。 があるように思えます。 1.に属する指摘点としては、(英文版を基にしています) ■9枚目の燃料の中性子捕獲による核図表上の移行方向が変です。 (その後のα崩壊、β崩壊も合わせて考えても) Minor Actinides と書いてある辺も少々ずれておるような。 ■20枚目の元素による性状の区分の一部が少々ミスリーディング。 セシウムはガスとすべきです(事故時の高温下では)。 事故の際、まず警戒すべきは; I-131(t1/2=8.06d) , Cs(セシウム)-137(t1/2=30y) の2核種ですが、これらのものが広がりやすい事の原因の一つが「気化しやすい」ということ。 この間違いだけは、単なる技術的ミスでは済まない話に思えます。 確かにCsは水に溶けやすいこともやっかいなことの一つですが。 ■上記のことから例えば22枚目のIn steam は、希ガスだけでなく ここに I、Cs を記載すべき。 23枚目以降のスライドにおいても、これら2元素はsteam 相に 2番目の、総論解説としての妥当性の点では、 ■核図表まで示して、マイナーアクチノイドにまで言及している一方で、 今回、物事をやっかいにしている崩壊熱に関する記述はあまりありません。 ■マイナーアクチノイドは事故の時というよりは、安全に運転しきった 核燃料サイクルの後の、高レベル廃棄物処分で問題になる核種。 恐ろしく超寿命、かつ内部被曝上やっかいなアルファ線を出しますので。 しかし、少なくとも今回の事故のケースでは、ウラン燃料での運転中にも 生成するプルトニウムと同様、もっとも警戒すべき核種ではありません。 ■一方、崩壊熱に関しては、炉の停止直後も、運転時の5-7%の 崩壊熱出力があるが、これは1日経つと0.3-0.5%まで減る、 さらに10日経つと 0.2%(停止直後から比べても1/20以下)にまで 減りますので、炉心の方は当初に比べずいぶん楽になってきているはずです。 (本稿の後半、広瀬隆氏への反論のところに、簡単な崩壊熱の見積もりを記しました) 確かに、「崩壊熱」はごちゃごちゃのものの寄せ集めで、理学部の 先生のご興味を惹くようなものではないのかも知れませんが、事故対策の 実用上極めて重要と思います。 ■また、総合的な危険性を占う上では、喪失しかかっている閉じこめ機能; 被覆管、圧力容器、原子炉格納容器の今後の健全性に関する見通し などが重要ですが、これらもほとんど記載されていません。 ───【要点】──────────────────────────── そう、こういうときには、正しいことをお伝えすると共に、重要性の メリハリにも気を付けるべきかなぁと感じます。 ★失礼かも知れませんが、理学系の方のこの手のは、 「大事なのはそこじゃないだろ」っていうのを感じるケースがしばしば。 ─────────────────────────────────── もちろん31枚目のスライドの結論、特に地球の放射能汚染を減らすには、 ・・・石炭火力を止めるのが一番、っていうあたり、激しく同意なのですが。 (なんと、日本語版を作るときに訳者の方々は、この部分を削除してしまっている!) 広瀬 隆氏のインタビュー一部には「とんでも」番付、東の正横綱、とのかけ声もかかろうかと思いますが(なら西は桜○淳か)、そういうつもりで見てみますと、意外と裏切ってくれます。何点も激しく同意しました。が、「エネルギーは他にもいろいろあるから、核兵器開発のための隠れ蓑としての原子力開発は止めるべき」という基本主張は全く同意できません。 反論すべきところを挙げても仕方がないので、激しく同意した部分のみを列挙します。■空間線量「率」シーベルト/時を1回のレントゲン撮影と比べることの愚かさを指摘。 但し、時間変動がある測定のピークの値に、いきなり1万を掛けろ(概1年の 時間数)、と言うのは、少々暴論。 これは、空間線量値の時間変動を良く押さえてから議論すべき。(本稿の更に下の方に、3月15日の東海村での空間線量の時間変動を載せています) しかしながら、地面に固着された汚染物由来の線量で、時間変動が少ないならば、その時は是非、広瀬流で考えるべき。そう言う状況で、/時を無視するのは、アホです。 ■外部被曝と内部被曝を区別しろ。 これはメディアの不勉強もあり、外部被曝としての空間線量の問題と、内部被曝をもたらす汚染の危険性が峻別されずに報道されている点、未だに気になります。 ■マグニチュードと震度のアナロジーで、放射能量と被曝線量を語るのも秀逸。 ■最後の「基本はカネです」、激しく同意。 全体を通して、流石作家の方と思いました。 ふと思い出したのが毎年出ていた徳大寺さんの車の本のタイトル; 「良い車の選び方」ではなく、「間違いだらけの・・」。 そう、人間はポジティブな情報よりもネガティブな情報に敏感なので、 そっちの方で「作品」を作る方が、名前も本も売れるでしょう。 そう言う意味で、ご本人も語っておられる「基本はカネです」というのは、 まさにそういったビジネスモデル。でも、そのためには勉強しなくてはいけなくて、彼はアホなメディア(例えばこのビデオのインタビュアー)よりは 遙かに勉強しておられる。 ★そういえば、計算までしたので、一点だけ反論を載せます。 「崩壊熱は無限に続きます」 定性的、理学部的には正しいですが、工学部的にどうか? 停止から既に10日以上経っていますから、現在の崩壊熱は、 定格熱出力(電気出力の3倍)の0.2%以下。 一番小さい1号機は定格46万kWe(この最後のeは電気出力の意味)なので、 現在の崩壊熱出力は、厳しめに見積もっても2.5MWくらい。 これを、40.8kJ/molの水の気化熱で除去するとして、毎時4トンの水(100℃)が 必要な勘定になります。 4トンというとチト多いようにも思いますが、毎時ですからねぇ。 ウチの風呂桶の給水系ではさすがに力不足か(でも1時間全開すると1トン; 1mx1mx1m くらいの水量にならないか?)といったレベルです。 原発のご立派な配管からすれば、多少くたばっていても、へのかっぱのハズ。 東海村付近の空間線量にわかに脚光を浴びてきた、村のモニタリングポストの測定値のリアルタイム・ネット公開。3月15日は東海村の空間線量が上昇し、東大が文科省に通報したことが報道されていましたが、小生も早朝から標記モニタリングポストの値を書き留めており、その詳細なデータは下記の通り。異常な値が出始めたので、正直、びびりました。なんせ、通常値は50位なので、ピークでは70倍。しかし、グラフでもわかる通り、2時間くらいで汚染の激しい大気は通り過ぎていったようです。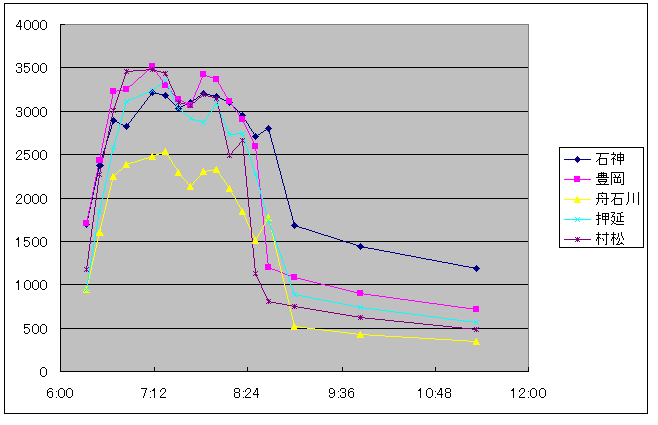 2011年3月15日朝の東海村モニタリングポストの値の変化(縦軸:nGy/h、横軸:時刻) 一方、この一瞬70倍なんてナンボのもんじゃい、と思わせるデータもネットに転がっており、例えば; 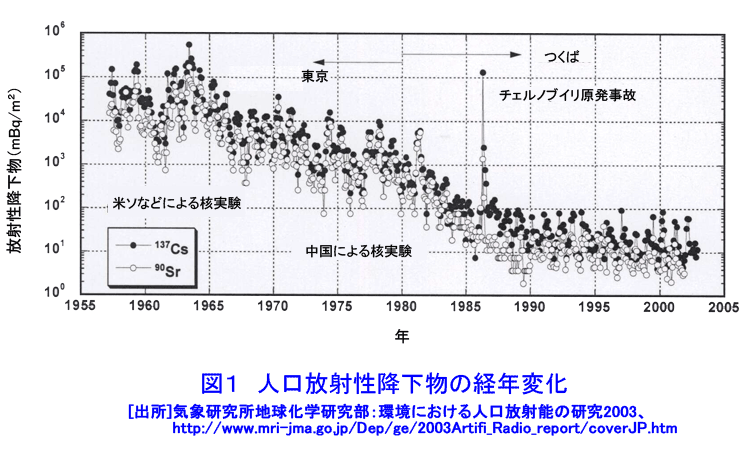 縦軸が、ちょっとなじみの薄い対数目盛なので気を付けてください。小生は、1956年生まれなので、放射線感受性の高い乳幼児の時期は、と思って上のグラフを見ると、・・・見たくもないような値が並んでいますが(今の1万倍!)、まぁ、それでも今日まで、元気にしてますんで、ご心配なく。 |
ホームページへ