計算法新ペリア方式の計算は、
この演算による効果実力差を1/3に圧縮します。別な言い方では、18ホールじっくり勝負する結果を、2ホールでの勝負と同じくらいの「ばくち」に換算します。 その理由は、以下で・・・。
計算法の解析新ペリアの計算の精神は、統計的な誤差を含むデータに対する和や差に関することで、放射線計測にも一脈通じるところがあります。今、データA、Bが誤差a、bを含むことを複号を用いて、 (A±a)、(B±b) と書くことにします。その和や差は、 (A±a)+(B±b)=(A+B)±SQRT(a2+b2) (A±a)−(B±b)=(A−B)±SQRT(a2+b2) となります。もちろんSQRTは平方根を表します。 例えば、同じ測定を100回繰り返してその和をとると、当然、測定値の中心値は100倍になりますが、誤差は10倍にしかならない。従って、得た結果の和
ある人の各ホールあたりの平均オーバーパー数(例えばHDC36の人なら2)をA、実際にプレーしたときの打数の誤差をaとしたとき、全18ホールでのオーバーパー分;GROSS+は;
さて、問題は引き算;
新ペリアによる算出HDCは、
HDC = 1.2 x Σ(A±a)j ; jは1から18のうち12個
結果の解釈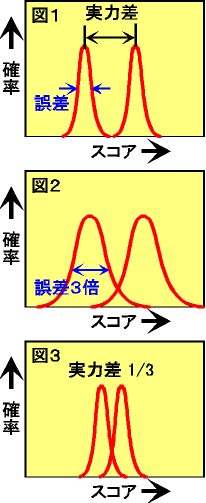 新ペリアによるスコア換算後のR値は、生値のR値の1/3しかありません。
新ペリアによるスコア換算後のR値は、生値のR値の1/3しかありません。今、実力差がXである二人の対戦を考えます。おのおのの18ホールの得点の分布の様子は例えば図1の様になります。これを新ペリア換算しますと、実力差の尺度を一定に考えて、誤差分布は3倍、図2の様になります。2人の対戦結果の勝ち負けを考えると、逆にこれは、誤差分布を様子を元のままにして考えると、実力差を1/3に圧縮した様になる、とも言えます。 ま、新ペリアってのはせっかく18ホールやるのに、「2ホールで勝負をつける」というのと同程度のばくち加減、一発勝負的にするものです。 しかし、「どうせ新ペリアだから一生懸命やっても仕方がない」ってなことをおっしゃる実力者の方がいらっしゃいますが、これは間違いです。生値でスコアを1縮めることは、平均換算後のNET値を0.2でも縮めることになるのですから。これは冒頭HDC計算のために、12ホールの結果から18ホール分のオーバーパー分を求める際に、1.5でなく1.2しか掛けていない事に由来しています。 「新」でないペリア方式に比較して「旧」ペリアでは、隠しホール数が1ラウンド中6ホール。算出HDCはこのホールのオーバーパー分を3倍かつ0.8倍してHDCとする、 ってなことですが、「新ペリアでは旧ペリアでの隠しホール数を倍加して、変動による運不運の影響を受けにくくしたのが新ペリア」と専門書にもありますが、これは半分正しくて半分間違い。なぜなら、新ペリアでは、逆に少ない「非隠しホール」で勝負が決まります。両方式の本質的な差は実力差圧縮率の差。新ペリアでは上述の通り圧縮率3ですが、旧ペリアでは圧縮率は幾分高めの5.7。その分、新ペリアの方が上級者有利な方式といえます。 さらに、隠しホール12ホールをパー48になるように選ぶことから、全てをミドルホールから選ぶのは不可能で、ありがちなのが各ハーフでロング1、ショート1、ミドル4という組み合わせ。そうすると、ハーフの中の非隠しホール(勝負ホール)3つは、ロング1、ショート1、ミドル1ってなことに、通常の配分比率よりロング、ショートに強い人有利な組み合わせになりがち、ってことも言えます。
おわりにゴルフって一回行くと2万円くらいかかる結構贅沢なお遊びですが、コンペとか言うとゴルフ場に払うお金の他に、景品代とられて、でも毎回景品もらう人きまっててだんだんいやになります(>あまりもらえない自分)。 ハンディキャップ(以下HDC)を自己申請すると不正が生じがちとか言うことで、ある時、職場のちょっと大きな大会で「新ペリア方式」というHDC計算方法を採用することになりました。当時(1990年ころ)はまだdosの98ノートとBASICなどという非力な組み合わせでしたが、何とか終了後の現場で40人分ほどを演算処理して順位を決めることが出来ました。このような(新)ペリアという計算方式は、しばしば用いられているようなのですが、生のスコア値に、このような演算を施すことはどのような効果を持つことになるのか、ちょっと検討してみました。 なお、本講座は、当大学でも異例の人気講座で、1日100人ほどの方にご利用いただいているようです(ご支援、多謝)。そうすると、学長の自己満足的な書き方よりは、もう少し親切せねばなるまいと考えまして、重要そうな話(計算法自体と計算効果の結論)を最初に簡単にとりまとめ、暇そうな蘊蓄は後半に回すことに致しました。(11/03/06) |