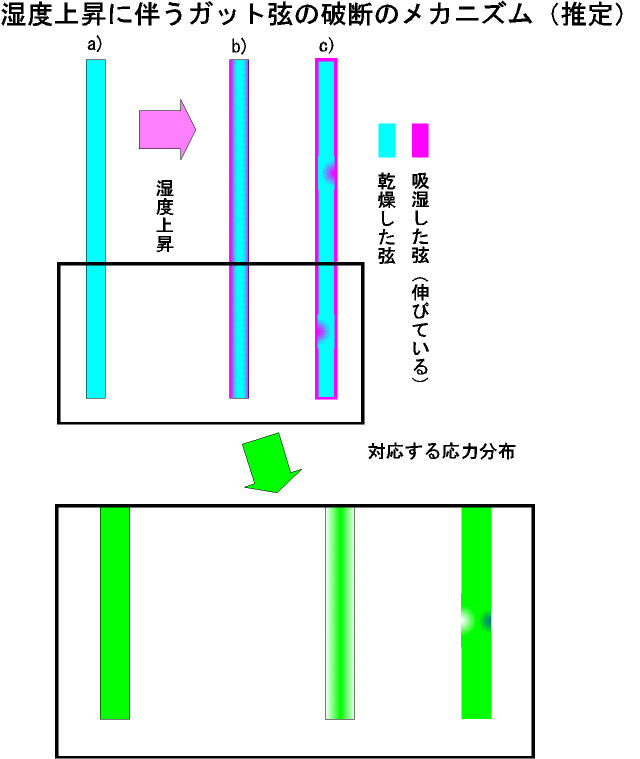ガット弦練習環境の劣悪なことが多い○響では、昔バイオリンにガット弦を張っていったところ、練習中にどんどん音程が下がり、大変懲りてしまいました。ガット弦はそれ以来ご無沙汰で、最近は、もっぱら、ナイロンの糸を張っております。 我々、4本の弦しか張っていないバイオリン属に比べ、ハープには47本も弦が張ってあるそうですが、低音側から、鋼、ガット、ナイロンと使い分けておられます。鋼とガットの間で「いいのか?」というくらい音色が変わるのですが、中音以上の領域で、好きなようにガット張ったり、ナイロン張ったりとい訳ではないようです。 一つには、弦の本数が多くて響板に掛かる負担が大きいのでやたら規格外の張力の糸を張ってはマズい、しかも、同じように弦の多いピアノに比べても、ハープの場合は板面に垂直に弦の張力が掛かることも関係しておると考えられます(ピアノの弦の張力は、板面に平行な方向)。従って、ハープの場合通常はかなりな数のガット弦が用いられているわけですが、ハープの方によりますと、梅雨時、これが結構切れるのだそうです。 ガット弦は湿度が上がると伸びる、従って張力は下がる その結果、バイオリンの場合は音程が下がってしまうのですが、そうすると、ハープの場合は弦が切れると言うこととは、なにやら単純には納得がゆきません。そこで、いろいろ考えまして、次のような事なのかなぁ・・・と。
まず弦も環境も乾燥しているときに、正規にチューニングした楽器(a)の周辺湿度が上がりますと、弦も吸湿するわけですが、もちろん表面から吸湿し、過渡的な段階では弦の湿度は弦の中心と周辺部では不均一になります。(b) この場合も、弦全体の長さにわたって表面から均一に湿度が侵入していく場合は 、弦全体の張力が低下し、吸湿した周辺部分の応力が低下するだけで、中心部の応力が特段増加することはありません(楽器本体は、一応、剛体として)。 しかし、天然素材のガット弦では、実際の吸湿は、素材に内在する欠陥、不均一性に由来して、弦の長さ方向に関しても、まだらに生じると考えられます(c)。この場合には、全弦長に対しては、局所的である吸湿部分の伸びは、弦の乾燥部分の弾性変形で吸収するため、弦の張力の低下は僅かに留まります。 一方、局所的な吸湿が生じた近傍の弦の断面を考えると、吸湿部分が伸びてしまうためにこの部分は張力を充分に負担しないようになり、弦の張力は断面の一部である、乾燥した部分によって主に担われることとなり、この部分の局所的な応力は、当初の弦全体が乾燥していた時よりも高くなります。 こうして高まった応力が、素材の破断強度を超えると、その部分は破断してしまします。そうすると、残った部分で張力を支えなくてはなりませんが、同様に吸湿プロファイルの不均一生に由来して、張力の担い方が不均一になり、断面の各部が次々と破断するということになります。
ハープの持ち主の方によりますと |